|
依頼は思わぬところからやってきた。
アパートの隣に住む美人探偵麗香から、半ば強引に引き受けさせられたのは昨夜のことだ。
同業者、つまり麗香と同じ探偵を生業とする 大沢 透 という人物が一週間前から行方不明だというのだ。
仕事柄、依頼によっては何日も家を空けることは珍しいことではないが、行き先を誰にも告げず、
恋人にも連絡を取らずに姿を消すというのは初めてのことだった。
大沢の恋人、稲村 杏子 が大沢の居所を探して欲しいと麗香に泣きついたのだが、超多忙探偵である
麗香は手が廻らず、暇を持て余している隣人へ、笑顔と共に押し付けたのだった。
「ったく…。麗香の奴、ちゃっかり仲介料を取るとか抜かしやがって…」
男は、相変わらずブチブチと文句を言いながらコーヒーを啜っていた。
「あんたね、せっかく麗香さんが好意で回してくれた仕事でしょ?もうちょっと、真面目にやったら?」
ミニハンマーをちらつかせながら、パートナーの香が睨みつけた。半ば脅しである。
「いいんです、香さん」
依頼人である杏子が重い口を開いた。
大沢が行方不明になってから、この数日間でかなり憔悴しきっているのが見て取れるほどだ。
「警察も手掛かりがないからって真剣に探してくれないし、挙句の果てに家出じゃないかとまで言うので、
私、困ってしまって…。もう、冴羽さんたちしか頼れる人はいないんです」
「杏子さん…」
震えるような声で話をする杏子に香は同情している。
あいつはこの手の話に弱いんだよな、と撩は頬杖をついて香を眺めた。
「私たち、来月結婚する予定なんです。透が私に何も言わずにいなくなるなんてこと、考えられない。
お願いです、冴羽さん、香さん。透を探してください!!」
悲痛な面持ちで語る杏子に、香は杏子の手を取って握った。
「大丈夫。私たちに任せて。大沢さんは必ず見つけ出してあげるから!」
「ありがとうございます、香さん」
あ〜あ、安請け合いしちゃって。知らんぞ、オレは…。
撩は二人のやり取りを聞いていたが、ふと思い出したように切り出した。
「杏子さん。大沢が最後に調べていた会社、何て言ったっけ?」
「花岡商事という会社です。貿易関係の調査だから難しくないって言っていましたけど。それが何か?」
「…いや。なんでもない。ちょっと確認したかっただけだ」
それきり黙って何か考え事をしてしまった撩を、香は不思議そうに見つめていた。
「大沢さんと杏子さんは、おつきあい長いんですか?」
撩が情報収集に出かけてしまうと、リビングには静けさが漂う。
重い空気を少しでも和らげようと香は当り障りのない話をもちかけた。
杏子は昔を思い出したのか、少しだけ顔を赤らめて話しはじめた。
「私たち、中学時代からの腐れ縁で、ただの仲の良い友人として長い付き合いをしていたんです。
一緒に遊びに行ったり、悩み事を相談したり、透が私の傍にいるのが当り前って思っていました。
だけど、その居心地の良さに慣れてしまって自分の気持ちに気が付かなかったんです」
「大沢さんのことが好きなんだって事?」
「ええ。去年、透から告白されて初めて、私もだわ、ってやっと気が付いたんです。
可笑しいですよね。妙に照れ臭かったけれど、それからは ちゃんとした交際を始めたんです」
「へえ…」
香は嬉しそうに話をする杏子に、自分を重ね見ていた。
相手の存在が近すぎて気持ちに気付かなかった、いや、気付かないフリをしていたあたしと撩。
いつからだったろう。私が撩のことを一人の男として意識しはじめたのは…。
パートナーとして一緒にいることに慣れてしまうと、それ以上の関係に進むことは
それまでの二人の関係を壊しそうで、崩してしまいそうで、未来が見えなくて、怖かった。
そう思ったのは、たぶんあたしだけではなかったはず。
でも、お互いに一歩踏み出したからこそ、今のあたしたちがいる。
杏子さんも大沢さんとその一歩を乗り越えてきたんだわ。
「香さんは?冴羽さんとは…」
杏子から急に話を振られて、思わずしどろもどろに返事をする。
「あ、いや。あたし達は、し、仕事上のパートナーなわけで、別に、その…」
香の慌てぶりが余程可笑しかったのか、杏子がここへ来てはじめて笑顔を見せた。
「ふふっ 香さんって、正直ね。顔に出てるわよ。 幸せですって」
「え?あは、は。そ、そんなことないと思うけど・・・。あはは・・・」
ムキになって否定することではなかったけれど、コロコロと笑う杏子を見ながら、
彼女こそ、大沢さんと幸せになってもらわなきゃいけない。
香はそう強く願っていた。
撩が戻ってきたのは、もうすぐ日付が変わるという頃だった。
「どうやら大沢はやっかいな事に首を突っ込んじまったらしいな」
出かけるときとは違って険しい顔でそう言う撩に、香は微かな不安を覚えて眉根を寄せた。
「どういうこと?」
「花岡商事は家具の輸入専門の会社だが、商売はうまくいっていなかったらしい。
負債返済の為に、香港の組織にまるめこまれて麻薬の密輸入に手を出した。…と、簡単に言うとそういうワケ」
「ま…麻薬?」
杏子は青ざめた。
「ああ。サツも周辺を嗅ぎ回っているらしいから、かなり切羽詰ってきてんだろうな。
恐らく、大沢は奴等に見つかって捕まっているんじゃないかと思う。無事でいればいいが…」
「!」
「撩っ!」
「わかってるよ。乗り込むなら早い方がいい。香、準備しろ」
武器庫へ降りていった香の後ろ姿を見届け、撩は佇む杏子に尋ねた。
「あんたはどうする?ここに残るか?」
パイソンを取り出し、弾を点検する様を杏子は震えながら見つめる。
「私も…私も連れて行ってください。お願いします!」
指が白くなるくらいぎゅっと握り締めながら力強く言った。
「そう言うだろうと思ったよ。だが、危険だぞ」
「わ、わかっています」
その目に迷いが全くないのを読みとり、撩は軽く頷いた。
横浜に花岡商事の所有する港湾倉庫がある。恐らくそこだろう、と、撩は目星をつけていた。
車を目立たない場所へ停め、三人は身を隠しながら目指す建物へと近づいていった。
「あれだ」
顎で指し示した先にある比較的新しいように見える倉庫は、周辺の倉庫とは明らかに雰囲気が異なり、
そこだけ厳重に数人の見張りがうろついている。
「杏子さん、あんたは香から離れるなよ」
目の端でコクリと頷く頭を確認する。
「行くぞっ!」
声を合図に三人は飛び出していった。
見張りを難なく倒して倉庫の中へ足を踏み入れると、十人程の男たちが振り返った。
「何だ、おまえ達は!」
「いやね、ちょっと人を探しているんだよ。恐らくここにいるんじゃないかと思うんだが」
銃を片手にゆっくりと近づいてくる撩は、体中から恐ろしいほどの気迫を発している。
その気迫に負けて一歩も踏み出せずにいたリーダーらしき男は、蒼ざめながら答えた。
「な、何か勘違いしていないか?ここは家具倉庫だぜ。人なんかいるわけがない」
男が指し示した先には、木箱から開梱されたばかりの真新しい家具が並んでいた。
「ふ〜ん。家具倉庫、ねえ」
ジロリとあたりを見回した撩は大きな鏡台に目を止めた。
近寄って鏡面を上から下へと手の平で撫でると、男は明らかに慌てた様子で撩に駆け寄った。
「そ、それに触るな。高いんだぞ!壊れたらどうするんだ」
ふん!わっかりやすい奴。
撩は男に向かってにやりと笑いかけ、何も言わずに鏡面を撃ち抜いた。
ガシャーン ――!!
銃声と共に鏡が大きな音を立てて砕け散る。辺りには白い粉がふわりと舞った。
「へえ。最近の鏡って、おしろい入りなんだな」
ふざけた口調で唖然とする男達をからかい、小指で粉をすくってペロリと舐めた。
「楽しい夢が見られるおしろい、か」
「こ、このやろ〜!!」
怒った男たちが銃を向けるより早く、パイソンが火を噴く。
香も近くにいた男に廻し蹴りを入れて撩を援護した。
トリガーを引くこともなく手にしていた銃を弾かれた男たちは、次々に手首を押えて倒れこんだ。
遠くから聞こえるサイレンの音が次第に大きくなる。
「観念するんだな。麻薬密輸の現行犯だ。もうすぐ警察がお迎えにくるぜ」
香の蹴りをまともに喰らって倒れている男の襟首を掴みあげ、締め上げる。
「おい、大沢はどこだ」
ぐっ…
喉元を締め付けられた男が苦しそうにうめく。
「ち、地下…」
視線の先を辿ると、階段らしきものが見える。
「ありがとよ」
ドスッと鳩尾に肘鉄を食らわし、三人は地下へと急いだ。
しかし、駆け込んだ地下室で三人が目にしたものは、血溜りの中に横たわる黒い塊。
その塊が人間であると判った時、杏子は悲鳴をあげた。
新宿へと走らせる車の中は、重い空気と沈黙が流れていた。
撩が駆け寄った時、大沢はまだ微かに息があった。
しかし意識はなく、腕や足の骨は折られていて、腹部にも銃弾を浴び、出血がひどい。
助かる見込みはほとんどないと言ってもよかった。
杏子の心情を察すると居たたまれない気持ちになる。
救急車が到着するまでの間、透にすがって泣き叫ぶ杏子を、誰も止めることなどできなかった。
ずっと一緒にいるって言ったじゃない!
幸せになろうって約束したじゃない!
私を置いていかないでよ…透!!
香の頭の中には、杏子の叫びが何度も何度もリフレインしていた。
あれが 撩だったら…
こんな仕事をしていたら、嫌でも考えなくてはならないはずだった。
パートナーになってから今まで、その存在がなくなる事を何度も考えては
そんなはずはない、と打ち消していたのだ。
泣き叫んでいたのは あたし?
アニキの時は泣かなかった。辛さを分かち合える撩がいたから。
撩がいなくなったら、いったい誰と分かち合えばいいのだろう。
そんな人 いるわけないじゃない…
運転席の撩は、今は手を伸ばせばすぐに届くところにいる。
でも、明日は?
明後日は?
来年は?
生きているという保証はどこにもない。
裏の世界で長年生きてきて、今まで無事だったというのが奇跡的なことなのだから。
助手席の窓を眺めると、自分の後ろに、運転している撩が映って見える。
通り過ぎる車のライトが一瞬だけ車内を明るく照らし、窓の虚像を青白く浮かび上がらせる。
灯りが過ぎ去ると、撩の顔が闇にまぎれて見えなくなった。
まるで蝋燭の火を吹き消したかのようにいなくなった撩を慌てて追い、香は窓に指をついた。
ふ、ふふふ…。
ばかなあたし。笑っちゃうわよ。
これが現実。
いなくなる撩を追いかけて、追いすがるだけのあたし。
「泣くな」
ふいに声をかけられ、え?と顔を上げる。
頬を熱いものが伝い落ちていく感触があり、初めて自分が涙を零していたことに気付いた。
「あ、やだ。どうして…」
知らないうちに勝手に涙が溢れてきていることに驚いて、慌てて手の平で拭う。
「ごめん…ね…。何か色々考えてたから、涙腺弱っちゃったみたい…」
心配かけまいと、無理に笑顔をつくってみせるが、巧くごまかせたとは言えないだろう。
撩はそんな香をチラリと見ると、黙ったままハンドルを大きく切って横道へ折れた。
しばらく走らせた後、公園の近くにある展望台の広い駐車場に滑り込むように車を入れる。
常夜灯の周りにはトラックなど数台の車が駐車していたが、撩はそこから離れた一角に車を停め、エンジンを切った。
車内に訪れた静寂に戸惑いを感じながら、香は撩の言葉を待った。
「何を考えてた?」
香は答えられなかった。心の中に消しても消しても浮かんでくる不安を、口にしてしまえば
楽になるかもしれない。だけど、そうすれば撩が苦しむのはわかっているから。
「……」
俯いたまま答えない香にやれやれ、と大きくため息をついた撩は、シートベルトを外して
ポケットから煙草を取り出した。ZIPPOの灯りで少し顰め面をした顔がオレンジ色に浮かび上がる。
ふーっと紫煙を吐き出すと、狭い車内に薄色の幕が拡がっていった。
「オレが死んだら、って考えたか?」
はっとした顔で香が瞳を見開く。
「ど、どうして…」
「長い付き合いだ。そのくらい判るさ」
そっか…と小さく呟く。
「確かに、オレ達は大沢よりももっと危ない橋を渡っているし、いつ死んでもおかしくない。それが現実だ」
「撩! やめて」
死ぬなんて、そんな言葉は聞きたくない、というように両手を耳に当てる。
しかし、香の細い手首は掴まれて、塞いだ耳から難なく外されてしまう。
「いいから、聞け」
撩はシートに沈んでいた香の体を引き寄せ、背中が折れるかと思うほど強く抱き締めた。
驚いて顔を上げた香の瞳をじっと覗き込んで放さない。
「オレはお前をひとりにはしない。絶対だ」
顎をそっと持ち上げられ、軽く触れるだけのキスを落とされる。
「それは、どういう…」
ひとりにはしない、とはどういう意味だろう。
お前より先に死なない、ということなのか、地獄でひとりにはしない、ということなのか…。
悩む香にもう一度唇を重ねる。
「心配するな」
「…撩」
「ずっと一緒だ」
撩の黒い瞳が語っている。
そうか、そうなんだ…
静かに目を閉じる。
熱い唇が再び重なり、深く、深く口付けていった。
二人で一緒に生きていく。
決してひとりにはしない。
神に見放され
運命の扉が閉まる時も
二人一緒だ。
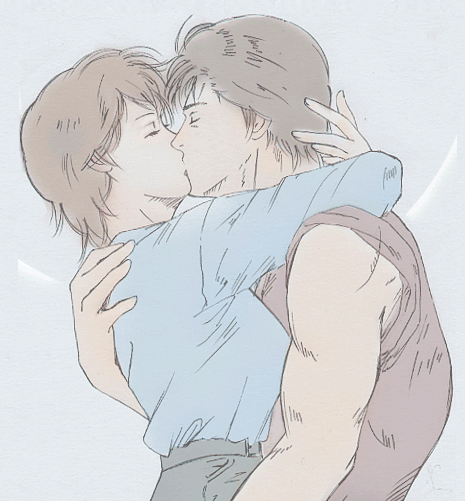
◇◇ エピローグ ◇◇
大沢の手術は成功し、後遺症は残ってしまうが命だけは奇跡的に助かった。
杏子からの電話を切り、香はソファに座るオレの方へ嬉しそうに振り向いた。
「そうか。よかったな」
「うん。杏子さんも、喜んでいたわ」
電話口でのやりとりを思い出したのか、ジワッと瞳を潤ませる。
おいおい。そんな顔するなって!
立っている香の腕を引いて、何も言わずに胸の中へと抱き込んだ。
すっぽりと収まる体は、何物にも替え難く心地が良い。
この腕の中にある温もりは永遠のものとは限らない。
そしてそれに気がついた者だけが、
この一瞬一瞬がどんなに大切な事なのか、知ることができるのだ。
「…撩」
「ん?」
「ずっと一緒にいるって、死ぬまでってこと?」
「なんだ、まだ心配してんのか」
苦笑しながら小さな鼻の頭をきゅっと摘まむ。
「だって…」
「ば〜か。 死ぬまで、じゃなくって、死んでも、だよ」
「死んでも?」
そうだ。
お前が先に死んだらオレは生きていけない。
オレが先に死んだらお前は誰かに殺される。
この世でもあの世でもひとりにはなれないんだ。
――― だからずっと一緒だ
至上の言葉を耳に落とすと、茶色の瞳から涙の粒が零れていった。
<了>
<あとがき>
ああ、懐かしいですね。これは閉鎖されてしまった『CHILD OF PROGRESS』さまに
捧げた作品で、久々のドラマ仕立てでした。このサイトの管理人 紗栄子様は、イラストがめっちゃうまくて、
彼女の描く撩チンに私がメロメロになったのです。私のサイトのバナーを作ってくださったり、
いろいろイラストをねだったりしました。オフでもはるばる北海道まで遊びに来てくださったり・・・
紗栄子さまの昔のイラは、当サイトのあちこちに散りばめてありますのでゼヒご堪能ください。
そうそう、二人の設定がカオリンの言葉を借りると「一歩踏み出した」ことになっていますが、
さらりと流してください・・・。あはは・・・。
撩 「おい、何かおかしくねぇか?」
ムツ 「は?」
撩 「何か足りねぇだろ。さらりと流せっていっても流せねえもんが・・・」
ムツ 「流す・・・?いやだわ、耳鳴りが・・・」
撩 「別にごまかすならいっけど・・・」
ムツ 「あは、あはは・・・何もごまかしてなんか・・・あらやだ。眩暈が・・・」
撩 「ついでに記憶障害ってか?なら、思い出させてやろう。オレたちはあの夜は・・・」
ムツ 「ワーーーーーッ!!」

|