Special Day
また今年も憂鬱な日がやってきた。
どうして世間はお菓子屋の商戦に引っかかるようにできているんだろ。
でも、この寒空の中でじっと順番を待つなんて真似、あたしにはできない。
行列を横目に、足早に待ち合わせの店へと急いだ。
ここに来る途中で必要な買い物をしたのだけれど、どれにしようかと迷っているうちに
あっという間に時間が経ってしまって、待ち合わせの時間に、既に30分以上遅刻している。
こうして歩いている間にも、時計の針の進むのがいつもより早いような気がしちゃうじゃない。
ああもうっ!また信号赤だわ。
いらいらした気分が憂鬱に拍車をかける。
どうして憂鬱なのかっていうと、あいつがチョコを誰に貰っただの、いくつ貰っただのって
煩いからに他ならない。そしてこれみよがしにあたしに聞かせるものだから、いい加減うんざり。
あれはあたしの反応をみて楽しんでいるに違いないわ。
しかも、毎年毎年ミックと数を競っているんだから、どうしようもないのよね。
行きつけのお店のお姉ちゃんたちから貰うチョコっていうのは、半分営業なんだから、
高級で美味しいチョコがたくさんあるのは当然なんだけど、日本初登場のチョコブランドの情報が
あたしよりもはるかに早く撩の耳に、そして、口に入っているっていうのは、
はっきり言って、あんまりいい気分じゃない。
あたしはそんな高いチョコをプレゼントしたことはないけど、そしてお姉ちゃんたちからのは
義理だってわかってはいるんだけど、やっぱり
『何か悔しい』
って気がするのよね。
自分でもホステスに嫉妬してどうすんのよ、って思うけど、もしかしたら本命チョコも混じって
いるかもしれないとか、撩がどんな“お返し”するのかしら、とか考えると、いてもたっても
いられなくなっちゃう。
そりゃあ、はっきり言って、私は毎年500円以上のチョコはあげたことはないですよ。
(だけど、あいつは尻尾振って喜んで受け取る)
手作りだって、前に大失敗しちゃったからそれ以降は作っていないし。
(あの時はもう一回溶かしてチョコドリンクにしたっけ・・・)
バレンタイン自体を忘れてしまったことも一度や二度じゃない。
(・・・・・・大汗)
思い返すとかえって墓穴掘りになりそうで、慌てて頭を振った。
バレンタインだからって特別な日にはしたくはないけれど、いつもなら照れてしまって、
ごまかしちゃうようなことも、不思議と言えそうな気がする。
だってね、ずっと一緒に暮らしていて、傍にいるのが当たり前の生活に慣れてしまったけれど、
ふと、これって惰性なのかなぁ、なんて考えちゃうこともあるのよ。
ずっと傍にいてくれるっていう確固たる保証はないし、自信もない。
さっきの行列にいた女の子たち。
たった一人のために一生懸命で、そして綺麗に輝いていた。
“ひたむき”?
ちょっと違うかな。そうね。
“一途”っていう感じよね。うん、まさにそう。
こんな歳になっていまさらとは思うけど、やっぱり受け取って喜ぶ顔が見たいのよね。
ちょっと照れくさそうに、鼻の頭をポリポリ掻いている、そんな顔。
高級チョコよりも、気持ちを込めたもので喜んでもらいたい。
だから、今年はスペシャルでいこうって決めたのよ。
重たい木製の扉を押すと、ガラン、と低い鈴の音が鳴った。
狭い店の中をぐるりと見回したら、一番奥の席で美樹さんがこっちと軽く手を挙げた。
「ごめんなさい!すっかり遅くなっちゃって」
「いいのよ。あたしもちょっと遅れたから気にしないで」
でも、カップの中はすでに空。
あたしから頼んで来てもらっているのに、こんなことになっちゃって。
今度お礼するから、と必死で言った私に、美樹さんは笑ってそれよりも、と切り出した。
「材料はちゃんと買えた?」
「あ、うん。初めてだからどんなのがいいか判らなかったけど」
ポケットの中から小さな包みを取り出した。
さっき、散々悩んで、真剣に選んで買ったものだ。
「これと、これを組み合わせてみようと思うの」
そう言って恐る恐る取り出して見せた物を、美樹さんはしげしげと眺めた。
「ね、どう思う?」
ちょっとだけ小首をかしげて何かを考えていた美樹さんは、にっこりと笑った。
「いいんじゃないかしら。きっと似合うわよ」
「よかった〜〜〜っ」
半ば脱力して机にうつ伏せたあたしを、美樹さんはちょっとちょっと、と小突いた。
「まだこれからじゃないの。安心するのは早いわよ」
そうだった。これから半日で完成させなきゃならない。
そう思ったら急に不安が押し寄せてきた。
だってあたしは、料理以外は、かなり、というか、とっても不器用なんだから。
「で、できるかな。あたしに」
「大丈夫よ、あたしがついてるじゃないの」
「お、お願いしますっ」
二人で顔を見合わせてくすっと笑った後、早速取り掛かることにした。
◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
その夜遅く、オレはチョコで溢れんばかりの袋を抱えて帰宅した。
ドサリ、と派手に音を立ててソファに落とす。
おかえり、とキッチンから出てきた香は目を丸くした。
「こんなに?」
「どーだ、スゲェだろ。今年はミックに大差をつけて勝ったんだぜ」
ふふん、と鼻で笑ったオレに、香は呆れたように目を細めた。
「あっそ」
「ケイコちゃんだろ、アケミのママだろ、リエにユカにミドリに・・・・・・」
「・・・・・・ばっかみたい」
その口調が、なんだか悔しそうに聞こえて、思わず笑みが漏れた。
ホント、素直じゃねぇんだから。
「たくさんあったって、これ、みーんな義理チョコでしょ?」
「別にいいじゃん。くれるっていうんだから。貰ったってバチは当たんねぇぞ」
「どーだか。どうせ、あんたからくれくれって強請ったんでしょ」
「んなことするかよ。まあ、誰かさんは黙っていると永遠にくれないけどな」
みるみる顔が、かぁっと真っ赤になった。
ほらな。
んな顔すんなよ。
ついつい、いじめたくなっちまうだろーが。
義理チョコなんか、何十個もらったってな、嬉しくなんかねぇんだよ。
つきあいの延長みたいなもんだ。
お前は余計な心配しているのかもしれないけどな、槇村香という存在を無視して
オレにマジチョコなんかくれる度胸のある奴なんか新宿界隈にはいねぇぞ。
オレが欲しいのは世界中でたった1個のチョコ。
お前はそこんとこ、判ってないんだよなぁ。
「お前はくんないの?」
「え・・・」
「だから、チョコ」
ぼーっと考え事をしている間に距離を詰められていたことにも気がついちゃいない。
慌てて逃れようとしているけど、そうはいくかってぇの。
身体を挟むようにして壁に両手をついたら、コクリ、と白い喉が上下した。
しばらくしてようやく観念したのか、ポケットから何やらモゾモゾと取り出した。
「・・・・・・はい、これ」
「サンキュ・・・・・・って、これなんだよ!」
「予算の都合上、それしか買えなかったのよ」
「はあ?」
オレの手のひらの上には、色気も何もあったもんじゃない、小さな板チョコが一枚。
パッケージに包まれているわけでもない、カードが添えられているわけでもないそれを見て、
ガックリと力が抜けた。
「マジ、かよ」
「ごめんね」
思わず溜め息をついたオレを見て、何故だか香は微笑んだ。
しかも全く申し訳なさそうじゃない。
なんでだ? とその違和感を探るオレに香は言った。
「ね。ちょっと目を瞑っててくれる?」
「ん?おまけにキスでもしてくれんのか?」
「何言ってんのよ」
冗談だよ、と大人しく目を瞑ったオレの左腕が香の手に包まれる。
「いいって言うまで開けないでね」
「わかってるよ」
こいつほど、感情が表に出やすい人間はいない、と思う。
嘘がつけないっていうのが、この商売をやっているとデメリットになってしまうこともあるが、
痛いほど伝わってくる感情に、救われることが多い。
だから、香が嬉しそうな顔をする時は、心の底から嬉しいんだ、ということだ。
湧き上がる妙な期待を抱えながら、オレは従うことにした。
少しの間、ゴソゴソと音がしていたが、軽い拘束感がしておや、と思った。
ちょっと期待とは違ったようだ。
「いいわよ、開けても」
「これって・・・・・・ミサンガ?」
自分の左手首に巻かれたものに目が奪われた。
ところどころ目が飛んで、縒れて太さもガタガタで揃っちゃいない。
だけど、その色。
紺色と、濃い緑色が複雑に編みこまれたそれは、見るだけでとても手の込んだものだと判る。
ミサンガの両端には小さな赤いビーズが括ってあって、手首で揺れていた。
「すごいじゃん」
「そ、そんなに上手じゃないけど・・・」
「だよな。目が粗い」
「ひ、ひどっ」
「でも、この色。すっげぇ綺麗」
よく見ようとライトに翳したオレの脳裏に、フラッシュバックのように昔の光景が浮かび上がった。
灼熱の太陽。吸い込まれそうな深い海と、南国の鬱蒼としたジャングル。
・・・ああ、思い出した。
むこうにいた頃、現地の人間がこれと同じようなものを巻いていた。
願をかけながら恋人の腕に巻くのだ。
風呂に入るときも、寝るときも、片時も外さない。
そして、それが自然に切れた時に願いが叶うのだと言っていた。
不器用な香がどんな思いをしてこれを編んで、
そしてどんな願をかけてこれを結んだのかと思うと、胸が痛い。
チョコのことなんか、どうでもよくなってしまった。
つか、何をそんなに拘っていたんだろうと、バカらしくなった。
オレが黙ってしまったからか、香が焦ってあんまりじっくり見ないでよ、と言った。
初めてなんだから、しょうがないじゃない、と、それを隠そうとする腕をそっと掴む。
「大事にする」
何を、とは敢えて言わない。
ミサンガだけじゃない。
お前の気持ち。
ふたりの命。
これからのこと。
全て、全て。
こんなバレンタインも悪くない。
今日はSpecial Dayだ。
ゆっくりと気持ちを確かめ合おうじゃないか。
<End>
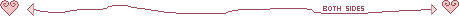
<あとがき>
超ぎりぎりのバレンタイン物ではあったけど、ちゅうもなければ●●もない。
ちょいと不完全燃焼でしたかね。ごめんなさ〜い。
皆様はどんなバレンタインを過ごされましたか?
私はまたしてもPCと格闘して大半を過ごしました。まったくラヴがありませ〜ん。
ムツ 「ミサンガ。いいねぇ」(ニヤリ)
撩 「見〜る〜な」
ムツ 「いいじゃん、減るもんじゃなし」
撩 「い〜や、減る」(と、隠す)
ムツ 「なんでよ」
撩 「お前の視線には塩酸が含まれていて、見たものが溶けちまうってまことしやかな噂がある」
ムツ 「な、何言ってんだよー」
撩 「オレが貰った義理チョコはお前の視線で全部溶けた」
ムツ 「あれは! あんたがヒーターの前に置きっぱなしにしていちゃこいてたからでしょーが!」
撩 「形はぐちゃぐちゃ、見るも無残な姿になった」
ムツ 「だーかーらー・・・」
撩 「そして、お前と目を合わせしまった不幸な奴は、皆、石に変えられちまう」
ムツ 「メデューサか!あたしはっ!」
撩 「ああ!あそこで犬が石になってる!」
ムツ 「あれはハチ公だろ!」(殴)
撩 「オレも石に変えられないうちに戻るわ、じゃな」
ムツ 「行っちまった・・・・・つか、逃げられた?・・・・・・ちっ」

|